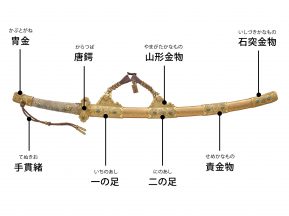大正天皇
1879年(明治12年)8月にお生まれになった「大正天皇」は、1912年(明治45年/大正元年)7月、事実上の即位となる践祚(せんそ:先帝が崩御された場合、またはその譲位により、天皇の世継ぎがその皇位を継承すること)を行なわれますが、生来病弱なこともあり1922年(大正11年)には「裕仁親王」(ひろひとしんのう)のちの「昭和天皇」を摂政に立て、事実上引退。
大正天皇は表舞台には戻らぬまま、1926年(大正15年/昭和元年)に崩御されました。
生まれつき病弱であった大正天皇は、軍務などに関してはおよそ不向きでしたが、和歌や漢詩などにその優れた才能を発揮されています。これは、大正天皇の母方の祖が、平安時代の「藤原北家」(ふじわらほっけ)から続いた名門の公家であったことが関係しているのかもしれません。
そんな大正天皇が詠まれた和歌や漢詩のなかには、刀剣を題材とした御製(ぎょうせい:天皇や皇族が、自ら作られた和歌や詩歌)がいくつかあります。
「磨きあげし つるぎを 床にかざらせて 明暮れに身の 守りとぞする」
こちらの和歌は、綺麗に磨き上げた刀剣を自身の守り刀とする旨を詠んだ作品。一見すると外敵や侵入者に対する備えが大切であることを詠んだようにも思えますが、「磨きあげし」と刀剣を手入れされたことを強調している表現から、不浄や穢れ(けがれ)に対する備え、つまり魔除けのための刀剣であったと解釈することが可能。
刀剣のなかには、神道でのお祓い神事(おはらいしんじ)に使われる作品もあります。それは、この和歌の題材となっているように、磨き上げた刀剣の穢れなき美しさが、神道において重視されている「清浄」と通じる点があるからに他なりません。
また、仏教での葬送儀礼の際、亡骸(なきがら)の上に短刀を置く慣わしがあります。これは、魂の抜けた亡骸に魔物が入り込むことを刀剣の霊力で防いでいるのです。
この他に大正天皇が詠まれた漢詩のなかにも、刀剣を題材にした作品があります。
寶刀(ほうとう)
<原文>
「自古神州産寶刀 男兒意氣佩來豪 能教一掃妖氛盡 四海同看天日高」
<読み下し文>
「古[いにしえ]より神州宝刀を産す 男児意気佩[お]び来たって豪なり 能[よ]く妖気を一掃し尽くさしめ 四海同[しかいとも]に看[み]ん天日の高きを」
<口語訳>
「古くから我が国日本では、宝刀を産している。男児たるものこれを1振佩びれば、たちまち意気軒昂[いきけんこう:意気込みが盛んで、元気いっぱいの様子]となる。妖しい気配を一刀のもとに拭い去ってくれるので、天下の人々は太陽が一点の曇りもなく、天空高くに光り輝く様子を目の当たりにするだろう」
大正天皇がこの漢詩を詠まれたのは、1915年(大正4年)のこと。その前年の8月、ヨーロッパでは「第一次世界大戦」が勃発。
当初は「セルビア王国」と「オーストリア=ハンガリー帝国」の戦いでしたが、「ヨーロッパの火薬庫」と形容されていたバルカン半島で戦端(せんたん:戦いの糸口)が開かれたため、両国の同盟国を巻き込んで、戦火はたちまちヨーロッパとアナトリア半島に拡大します。
この状況には、日本も静観するだけではすみませんでした。日本は、イギリスと「日英同盟」を結んでおり、イギリスと敵対していたドイツに宣戦布告せざるを得なかったのです。
このような未曾有の大戦に、否応なく巻き込まれた日本。漢詩・寶刀は、日本人全員が大きな不安を感じていた時局のもとで、詠まれた作品だったのです。
前述した通り、古来日本における刀剣が神事のお祓いや、魔除けの守り刀として使われてきたのは、清浄なる刀身に特別な霊力が宿ると考えられたことによります。漢詩・寶刀のなかの1句「能く妖気を一掃し尽くさしめ」とは、このことを踏まえた表現です。
大正天皇が第一次世界大戦勃発の翌年、あえて寶刀と題した漢詩を詠んだのは、日本国民ひいては世界中の人々が等しく抱いていた不安に、思いを馳せたためであったと言えます。この漢詩からは、健康上の不安を抱えつつも、ひたすら日本国民や世界の人々のことを案ずる天皇としての在り方を、垣間見ることができるのです。